阿曾村邦昭著『ミャンマー―国家と民族』(古今書院、2016年)
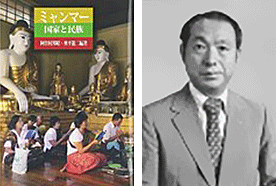
元駐ベトナム大使 阿曽村 邦昭
メコン地域に勤務、居住したことのある研究者や実務家の相互乗り入れの場としての 「メコン地域研究会」も創立以来8年半を超えた。
霞関会の会員で、この研究会の会員になっておられる方々も数名おられる。筆者は、この研究会の創立以来、会長のポストについてきたが、これまで、3・11以外には一度も休まず、毎月、例会を行ってきた。よく続いたものだと思う。 これだけの長い期間、まじめに勉強会をやっていると、当然、この地域の大国であるミャンマーに関してもいろいろな報告が出てくるわけで、これを「メコン研」だけの知見にとどめておくのはもったいないではないかという考えが生じてもおかしくないであろう。
例えば、昨2015年に「メコン研」は8月の夏休みと12月の忘年会を除いて10回の研究会を行ったが、ミャンマー関係は次の通り3回であった。
(1)4月20日
報告者 奥平龍二 東京外国語大学名誉教授
テーマ 激変するミャンマー情勢―国民教育法改正案をめぐって―
(2)10月19日
報告者 今村宣勝 (財)世界政経調査会第三部主任研究員
テーマ ミャンマー情勢:総選挙をめぐる動き
(3)11月19日
報告者 根本敬 上智大学総合グローバル学部教授
テーマ ミャンマー総選挙の結果と課題
前回、筆者が専任の編著者として例会での報告者のレポートをも入れて800ページ弱に上る『ベトナム―国家と民族―』上下2巻を刊行したのは、2013年8月のことであった。上下2巻の価格が税別で1万1,600円というのだから、これは売れないだろうと思ったところ、意外にもまずまずの売れ行きであった。
学会での評価もかなり高かったので、ほっとした。殊に第IV部の「日本軍のベトナム進攻によって北ベトナムで200万もの人々が餓死したのだろうか」は、評判が良く、いまのところでは「決定版」的な論考という評価さえも得たのである(ただし、外務省の関係者がどの程度読んでくれているのかは知らない)。
そこで、その年の暮れに、「メコン研」のミャンマー専門家である奥平龍二教授(元外務省員)に聞いてみると、「今度はミャンマー」をやりましょうよ」という積極的な反応であったので、今度は、奥平教授にも共編著者になってもらうことにし、本のタイトルは、ベトナムに関する前の文献名に倣い『ミャンマー―国家と民族―』ということにした。
前回の『ベトナム―国家と民族―』がやや、「民族」の扱いが少なく、「国家」中心であったことなどをも大いに反省して、今度は特に宗教と民族の問題とにかなりの力を入れようということで二人の編著者が一致した。そのうえで2013年末から本の構成案作りに取り掛かり、2015年後半に行われるというミャンマーの総選挙後、なるべく早く、出版するようにしようということで、執筆候補者への依頼やら転載の許可取り付け、写真探しなどの作業をはじめたのである。出版社は刊行した本が何ほどかは売れなければ困るので、出版はなるべくは世間の関心がミャンマーに集まっている時期を狙っ たわけだ。
『ミャンマー―国家と民族―』は、「メコン研」での報告者の論考を含むやや高水準の地域研究書であることは、前作の『ベトナム―国家と民族―』と同一である。対象は、一応、基本的な知識がある読者である。ただ、なるべく取り付きやすいように、23もの「コラム」を盛り込み、どこから読んでもある程度は「面白い」という構成にしてある。それだけに、執筆者の数も増え、ミャンマー研究の老大家から新進気鋭の研究者、熟練の実務家を網羅するようになったことも事実である。
ただ、この本を読めば、ミャンマーのことが何でも分かるというような性質の本ではないので、そういう本を求められる方は、ほかのその手の本を読んでいただきたい。前作『ベトナム―国家と民族―』の「はじめに」で述べたように、「本書は、特定のテーマに沿って少し専門的に問題を論じている。程度が少し髙いのである。絵でいえば、バロックの旗手カラヴァッジョ(Michelangelo Mensi da Caravaggio,15711~1610)のように、生々しい現実主義に加え、対象となる主題に強い光を当て、これを鮮明に浮き上がらせる手法をとっている。だから、ごちゃごちゃ述べ立てて、結局、何を言ってるのか分からないような論考はひとつも入っていないはずである。」という編集方針をこの本でも貫いたつもりである。
内容の解説を少ししておくと、本書は第Ⅰ部から第Ⅶ部まであり、いろいろな付属参考資料までついている大作である。付属参考資料の中では、第Ⅰ部第2章付属の「ミャンマーの王権神話」は本邦初の完訳で、内容それ自体が実に面白いのみならず、ミャンマー国民の主流であるビルマ族のものの考え方を学ぶのに役に立つであろう。第Ⅱ部第2章付属の、「日本におけるビルマ像形成史―国民国家形成史における他者認識―」も長編(転載)ではあるが、是非読んでいただきたい論考である。巻末の『付属参考資料』には、戦時中にビルマの国家元首兼首相をつとめたバ・モーの回想録のいわば「さわり」の部分、ビルマ式社会主義を推進したネー・ウィンの重要演説、アウン・サン・スー・チー女史の有名な”Freedom from Fear”の新訳、日本の財界人の現地での生の声を伝えている訪問記録を収録している。
とにかく、この本は中身が充実しすぎているため、800ページ弱全1巻の内容を全部読むのは大変だから、どこか関心のあるところを見つけて、読み始めていただければ、それでよい。それで更なる興味がわいたら、もっと読み進めばいいのだ。研究を始めようとするならば、巻末に「参考文献一覧」が掲載されているから、これを参考にして手に入りやすい文献からどんどん読み進めればよいのである。
第Ⅰ部は、「東南アジア史におけるミャンマー」である。日本人は「ミャンマーの人々は上座仏教の篤信者で、お坊さんがやたらに多い」ということくらいは知っているが、それ以上に、中国の影響が圧倒的に強いベトナムを除く東南アジアの「インド化」という「通説」が実は適切ではなく、バラモン教とかヒンドゥー教は東南アジアに入ってきたが、カースト制度など東南アジアでは受け入れがたい社会制度をも内容とするため、決定的に重要な影響を与えたのはスリランカで大成したパーリ語を聖典用語とする上座仏教の影響であることが故石井米雄教授の弟子である奥平龍二論文等によって明快に解き明かされている。英国植民地支配下のミャンマーが辿った社会経済変動や日本占領下のミャンマーの状況やミャンマーが独立当初に目ざした議会制民主主義国家形成の頓挫、国軍が作り上げようとした名目的な連邦国家形成の挫折、その結果としての軍事政権の長期継続も論じられているから、読者は、一応、古代から現代までのミャンマーの歴史をも学べるようになっている
第Ⅱ部「日本とミャンマー交流の歴史と伝統」では、17世紀初頭、ミャンマーの西側に存在したアラカン王国で日本人のキリスト教徒の一団が護衛隊を形成していた事実から始まって、日本人のビルマ進出は「からゆきさん」追随では必ずしもなかったのであるが、にもかかわらず、「「からゆきさん」先導型パラダイムが形成されたのは、ビルマなどアジア諸国を経済進出の対象としてしか考えない文脈においてであるという批判、竹山道雄の「ビルマの竪琴』はヒューマニズムに満ちた作品として日本でよく売れているばかりではなく、諸外国でも翻訳されているが、正にそれゆえに歪んだビルマのイメージを広汎に伝えているという論文、故会田雄次教授の『アーロン収容所』と『アーロン収容所再訪』などに見らるミャンマー観の紹介など、かなり重厚な論策が並んだ後で、「戦後の日本・ミャンマー関係」を扱った総括的な論考が出てくる。
第Ⅲ部の大作「大東亜戦争におけるビルマ―南機関と藤原機関―」は、日本軍のビルマ進出に先立つ日本の「南進」についてまず論じ、ついで大東亜戦争における「南進」が事前の準備もろくになく、追い詰められた日本が止む無くバタバタと決めた結果であり、ビルマ独立義勇軍の創設を担った南機関長鈴木大佐もインド国民軍の創設に関与した藤原機関長藤原少佐も全くの泥縄式にその使命を果たしたのであった。
彼等のビルマやインドの民族自決的な「独立」支持は、必ずしも軍中枢の見解を反映するものではなかったが、正にそれゆえに今日なおミャンマーやインドで高い評価を得ているというもので、インパール作戦に自ら進んで参加したチャンドラ・ボースの率いるインド国民軍とアウン・サンのビルマ国軍との比較、南機関長鈴木大佐と藤原機関長藤原少佐との比較論評など他では見受けられない分析が行われている。
ミャンマーを考えるときに、その独立との関連一つをとっても大東亜戦争は避けることのできない問題である。また、日本にとってビルマ戦線は、23万8000人の将兵を送り込んで、そのうち16万人7000人が戦没して故国に帰還することのなかった悲劇の地でもある。第Ⅲ部を読めば、このような戦争の重みをずっしりと味わうことができるであろう。
第Ⅳ部では、ミャンマーという連邦国家の内政と外交を扱っており、国軍の政治的地位、、ミャンマーが連邦国家とならざるを得ない多様で、深刻な民族問題の存在、現在の2008年憲法の概要と憲法改正へ動き、ミャンマーの憲法における仏教の位置付け、現代文学から見たミャンマーの政治・社会などを論じている。
ミャンマーは、ビルマ族が多数を占めるとはいえ、ASEAN諸国の中で内戦を含む「民族問題」に最も苦しんできた国家であり、このあたりは日本人一般、特に現場に暮らしていない日本人には理解が難しいのだが、第Ⅳ部を読めば、一応の理解は可能であろう。
第Ⅴ部は、経済問題を扱っている。 まず、「メコン地域協力と中国、日本、米国の対応」は、メコン地域に対する協力について、中国、日本、米国との間には、それぞれの思惑と特徴があり、それがミャンマーに対する協力にも反映されていることを論じている。日本とミャンマーとの二国間関係ではなく、メコン地域開発というより大きな枠組みの中で中国、日本、米国がミャンマーの開発にどう取り組んでいるのかを学ぶことは、中国の対外的な進出が盛んに報道されている今日、時宜にかなうものであろう。
その次が、ミャンマーの対外開放政策を中心にその経済と開発の現状を論じた論文で、最近行われた国勢調査についても若干言及している。付属資料1の「ミャンマー経済概況」と付属資料2の「主要経済統計表」は、最新のデータを基に作成されたもので、ミャンマー経済を概観するのに好個の資料である。 ミャンマーでも若年人口の減少がもう始まっていると聞けば、驚く人も結構いるのではないか。いわゆる人口ボーナス期間が比較的短いとなると、今後、ミャンマーは経済発展に全力投球しない限り、他のASEAN主要諸国に追い付くのが容易でないということになるであろう。
最近、ミャンマーへの日本企業の進出が報道されることが少なくないが、過去と現在の状況を簡明に説明したのが、「ミャンマーと日本企業」と題する論考である。
最後は、ミャンマーの農村社会と日本の農村社会を比較するという他に類例のない「比較」を試みた論文を掲載している。日本の村は「生産と生活の共同体」であるのに対し、ミャンマーの村は「生活のコミュー二テイ」であると言うのが結論である。執筆者は軍政下のミャンマー農村に実際に居住した経験のある―それ自体稀有の例であるが―農業経済研究者であることを付記しておこう。
第VI部は、「日本外交官が見たミャンマー」。第1章と第2章は駐ミャンマー大使を務めたことのある田島高志さんと宮本雄二さんの論考で、第3章は霞関会報(2013年1月号)に掲載された赤阪清隆さん(当時WHO中島事務局長補佐官)の体験記である。筆者としては、日本の外交官がどのようにミャンマーを見ていたのか、どのようなことをやっていたのかを世間一般に少しでも知っていただきたいという思いからこのような編集を行ったのである。
第VII部では現代ミャンマーの様々な社会問題を取り扱っている。仏教徒とイスラーム教徒間の問題、ジェンダー、ミャンマー仏教徒の死生観、筆者が顧問を務めているある国際NGOの現場報告、難民や医療問題と続いて、最後が「ミャンマーにおける日本語教育と有識者の対日理解」という若手研究者の論文である。
以上が、本書の概要であるが、何しろ価格が税抜きで2万円というのであるから、個人で買う人はまずいないのではなかろうか。このような本は、出版助成金の交付とか執筆者のなにがしかの経済的負担を伴うのが常であるが、今回も出版社側(古今書院)はそのような条件なしに出版に踏み切ってくれた。何ともありがたい。
編集のほかに「編著者」として筆者が何を執筆したのかと言えば、「はじめに」、第II部第3章の「竹山道雄『ビルマの竪琴』に見るビルマの虚像と実像」、同部第4章「故会田雄次教授のミャンマー観」および第III部「大東亜戦争におけるビルマ―南機関と藤原機関-」、同部附属資料1-2-3-4の解説ならびに巻末の付属参考資料I,III,IVの解説・翻訳ということになる。ページ数にすると索引や参考文献リストを除く本文739ページ中の160ページ弱くらいであろう。他方、共編著者の奥平龍二教授には、本の構成、執筆者への依頼、校正、索引、参考文献などでこれ以上出来ないほどのお世話になった。永い間の付き合いがなければ、こんな風にはいかないであろう。人的関係の重要性を今更のように身に染みて感じたわけである。
この本はかなりの大作であり、ミャンマー関係の文献としては内容、装丁、写真のすべてにおいて抜群のできではないかと自負しているが、泣き所もないわけではない。
それは、ベトナム関係の論文、著書一般についてもいえることだが、「日本語」で発表されると、せっかくの労作も国際的には殆ど無価値だということである。だから、今後、地域研究の文献を出すにあたっては-それまで生きているかどうかはわからぬにせよ-、是非英文での出版を試みてみたいと思っている。
(了)
