大島正太郎著『日本開国の原点: ペリーを派遣した大統領フィルモアの外交と政治』(日本経済評論社、2020年)
関場誓子(霞関会副理事長・聖心女子大学名誉教授)
はじめに
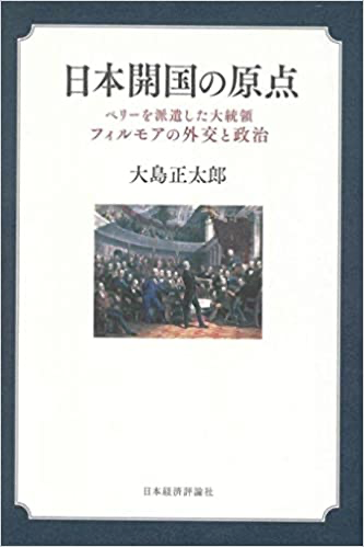
「歴史は状況と個人とが織りなす錦絵である」
本書を読み終えてつくづく思い起こされるのは、五百旗頭眞氏による、この指摘である。
著者の大島正太郎氏は、米国への留学経験も豊富な元外交官で、サウジアラビアや韓国の駐在大使を勤めた他、ジュネーヴの国際機関日本政府代表部大使として多国間外交の最前線に立った経験も併せ持つ。それだけに、氏の視点を通して明らかにされる政策決定過程は、どこまでも緻密かつ実証的だ。
日米関係の出発点がペリー来航にあることは自明であり、またその時ペリーがフィルモア大統領の親書を携えていたことや、そうした米国の行動の背景に太平洋における捕鯨船の避難地確保や中国との貿易拡大のための燃料・食料補給地確保の必要性があったこと、さらには米墨戦争の結果、ニュー・メキシコからカリフォルニア南部に至る広大な領土を手に入れて「太平洋国家」に王手をかけたことが、そうした必要性に拍車をかけたことも、よく語られる。
だが、そのほとんどが専らペリー一人に焦点を当てた説明であり、そもそもペリー来航の前提になる「太平洋国家」への基盤を整え、それを踏まえて日本への開国働きかけを決断し、そして、そのための特使としてペリーに白羽の矢を立てて開国に導いた人物、第13代アメリカ合衆国大統領ミラード・フィルモアに注目した記述は極めてまれである。
大島氏(以下著者)は、日米関係の出発点で重要な役割を演じながら、その後歴史の脚注に追いやられていったフィルモア大統領に光を当て、米国政治史における同大統領の盛衰を縦軸に、その過程で、建国以来米国を分断し続けた政治課題を、これまた従来見過ごされてきた様々な資料を掘り起こしながら、丁寧に論じている。その結果、一見日本の開国とは無縁に見えた様々な事象が、実は日本の命運に深くかかわっていたという事実が鮮やかに浮かび上がってくる。読者は、読み進むにつれて、一つ一つの支流が、やがて日本開国という表題のテーマに合流していく過程であったことに気づかされるのである。
本書の構成
本書は三部構成で成り立っており、第一部(1800年から1850年)では、フィルモアが大統領になるまでの政治情勢に重きが置かれている。この時期、米国内では、南のテキサスから西のカリフォルニアに至る広大な新規獲得領土を「州」として連邦に編入する際、「自由州」として編入させるか、それとも「奴隷州」として編入させるかで、南北の対立が激化していた。フィルモアが、ホイッグ党大大統領ザカリ―・テイラーの副大統領としてホワイトハウス入りしたのはまさに、そのような時期だった。歴史は、偶然と必然が織りなすドラマであり、党内事情で選ばれたに過ぎなかったフィルモア副大統領が、テイラー大統領の急死によって大統領に昇格したことは偶然以外の何物でもない。だが、本書は、その偶然が、アメリカの歴史、ひいては日本の命運に決定的な影響を及ぼすできごとであったことを丁寧に論じている。
本書の本丸ともいうべき第二部(1850.7-1853.3)では、大統領に昇格したフィルモアのもとで、「1850年の妥協」と呼ばれる諸法案が成立し、そのことが日本の開国に結びついていく過程が描かれる。
日米関係の脈絡と切り離して語られがちな「1850年の妥協」だが、これによってカリフォルニアは「自由州」として連邦に編入された。その結果、米国は紛れもなき「太平洋国家」となり、著者の言葉を借りるなら、「カリフォルニア州という太平洋に面した連邦構成州から太平洋とその先の東アジアを視野に入れることがむしろ必然となった」のである。
その流れの中でフィルモア政権が注目したのが、カリフォルニアと中国を結ぶ航路の途中にある日本だった。著者は、日本開国が、専らペリー提督の功績とされる従来の見方に疑義を呈し、大統領自身の年次教書や、後世の米国人研究者による論文等から、1850年の暮れまでにはフィルモア政権内で日本開国にむけた海軍艦隊による使節派遣の用意が出来ており、翌1851年初頭までには派遣が内定していたことを明らかにしている。
本書の締めくくりの第三部(1853-1874)では、フィルモアが退陣してから南北戦争までの10年間の意義が語られる。著者が、「日米関係の創成期」と位置付ける10年間だが、本書では、この「10年間」が米国だけでなく、日米関係にとっても極めて重要な意味を持つものであったことが明らかにされる。ペリーが浦賀に投錨して、フィルモア大統領の親書を浦賀奉行に手渡したのはこの時期であり、従ってほとんどの文献で「大統領親書」と呼ばれているものは、実際には、もはや「前大統領の親書」でしかなかった。にもかかわらず「大統領親書」として平然と日本側に手渡したペリーの胆力と、日本開国への関心が希薄だったにもかかわらずペリーによる開国努力を容認したピアース新大統領。本書では、それらが混然となって、1854年の日米和親条約、そして1856年の日米通商航海条約に結実していく過程が語られる。
日本にとっての僥倖-「1850年の妥協」によってもたらされた10年間の平時
以上を通読すると、太平洋国家への道のりを経て日本開国へという流れが決して一直線ではなく、歴史の歯車がほんの少し狂っただけでも、全く別のシナリオがあり得たという思いが背筋を走る。著者は、「(日米の)外交関係樹立が米国における南北戦争勃発までに完了していたことは日本にとって大きな僥倖であった」という。米国は、1861年以降、4年間に及ぶ凄惨な内戦とその戦後処理に忙殺されることになり、幕末維新の日本に関与する余裕がなかったからである。そして、その僥倖はフィルモア抜きには語れない。
「1850年の妥協」によって米国は太平洋国家への道を歩み始め、同時に、それによって奴隷制度の是非をめぐる米国内の対立が小康を得た。その結果、後に「妥協」の矛盾が表出して内戦が勃発するまでに10年の平時を確保することができた。その間に日米間では、ペリーの来訪による開国要求(1853年)、ペリーの再来訪による日米和親条約締結(1854年)、同条約の批准書交換(1855年)、ハリス領事着任(1856年)、日米修好通商条約締結(1858年)、同条約の批准書交換のための使節団訪米(1860年)、日米外交関係樹立(1860年)というように、以後の日米関係の基盤となる仕組みが全て整った。これらは、偏にフィルモアの「1850年の妥協」によってもたらされた10年という時間の恩恵に他ならない。
著者は、「歴史に『もしも』はないが、仮にテイラー政権が続き内戦となっていれば、日本に向けた遠征隊の派遣は、難しくなったと思われる。日本遠征隊の派遣は、当時の米国が、1840年代中期と1860年代初期の2つの『戦時』の合間の『平時』にあったからこそ可能であった」と指摘する。著者の指摘は、冷戦終焉と湾岸戦争という戦間期の一瞬にドイツ統一を成し遂げたコール政権の外交を思い起こさせる。「ドイツ統一への扉は、ごくわずかの幸運な一瞬にだけ、しかもほんのわずかに開かれていたにすぎない」。コールを支えたホルスト・テルチクの述懐である。開国当時の交通手段、通信手段、そして政策決定に要する時間を考慮すれば、10年という歳月は「一瞬」だ。日米両国は、その一瞬の隙間に滑り込んだとも言えるのである。
「歴史に『もしも』はない」というものの、「もしも」米国による遠征隊派遣がなかったとしたら、日本は一体どうなっていたであろうか。
著者は、英仏露の3か国が、アヘン戦争後の「南京条約」(1842年)で英国が大きな権益を得て以来、「次は日本と言わんばかりに」、日本への関心を高めていたこと、更にそこに日本と唯一通商のあったオランダの思惑が加わって、日本を巡る欧州列強の静かなゲームが始まっていたことに注目している。それは、すなわち米国の国内対立が長期化して、遠征隊派遣が後回しになっていたならば、米国による日本開国とは全く異なる展開もあり得たことを示唆している。本書は、果てしない歴史の“if”へのいざないの書でもある。
英仏とロシアが、クリミア戦争(1853-56年)の勃発で対日圧力どころでなくなったことも、米国による開国というシナリオの後押しをした。とは言え、当時の欧州列強の動きを見れば、日本の開国は早晩不可避となっていたであろう。現に日本は、1858年に、米国との通商航海条約締結に続いて、英、仏、露、蘭とも同様の条約を締結している。だが、著者は、「既に日本と外国との関係の基本的枠組みが、米国との間で最初に導入された最恵国待遇条項の下にあり、英国を含めいずれの国も他国より有利な条件を引き出すことが出来なくなっていた」と指摘する。遠征隊派遣に触れた1852年の年次教書でフィルモアは、「遠方の地を植民地として従属させることを容認していない憲法体制を持つ米国は、他のいかなる国より大いに有利な立場にある」と述べており、そうした姿勢を国是とする米国によって開国がなされたということは、日本にとって幾重にも幸運であった。
日本開国もう一つの舞台裏-オランダによる側面支援
ところで、欧州列強中、唯一日本と通商のあったオランダは、遠征隊派遣をどのように見ていたのであろうか。実は、遠征隊派遣に当たってフィルモアは、オランダに支援を求めている。自国の独占的地位が脅かされることを警戒したオランダは、当初、米の機先を制して日本に開国を迫るものの、その後は米国を側面支援する方向に舵を切り替える。著者は、こうしたオランダ側の微妙な動きを、既存の研究論文はもとより、ウエブスター国務長官と在オランダ米国公使フォルサムとの公信のやりとりや、フィルモア大統領にあてたフォルサム公使の私信等をもとに多角的に検証し、そのことが著者も自認しているように、ペリーの日本遠征を「立体的に」把握することに繋がっている。
特に、フォルサム公使がフィルモア大統領に宛てた私信は、オランダへの協力要請の背景にフィルモア大統領とフォルサム公使との個人的なつながりというアセットが存在したことを示すものとして興味深い。著者は、ごく些細な手がかりを起点に、バッファローの歴史博物館図書館に保管されていた私信のフィルムに辿り着いた。フォルサムの私信に着目したきっかけは、著者の「外交官としての個人的経験から」、在外の公使が大統領に直接私信を送ることを不思議に思ったからだという。外交官の勘働きの賜物と言えよう。本書には、この私信の写真も掲載されており、読者は長年陽の目を見ることのなかった歴史の舞台裏を垣間見ることができる。
ペリーはフィルモア「前」大統領の親書をどう扱ったか
著者の、外交官ならではの視点を感じさせる場面は他にもある。ペリーを任命し、遠征隊出航の際には自らアナポリスまで出向いて見送ったフィルモアだが、この時点で既に、次期大統領は民主党のピアースになることが確定しており、ペリーが「フィルモア大統領」の親書を携えて浦賀に投錨した際には、ピアース政権の時代になっていた。著者は、ペリーが、フィルモア大統領の親書に添えたペリー自身の「皇帝陛下(将軍)」宛て書簡の中で、大統領の固有名詞に一切言及していない事実に着目している。通常は砲艦外交ばかりが強調されるペリーだが、実際はアルフレッド・マハンの先駆けとも称される海洋戦略家であり、いずれ米国が太平洋を支配する時代が来ると確信していた。この一件は、そうした確信を背景に、その拠点として、日本を何としても開国させなければならないという周到で緻密な意図を伺わせる場面である。一件、見過ごされがちな事柄だが、外交交渉最前線の緊迫した場面に身を置いた著者ならではの着眼と言えるだろう。
もしも、ペリーが愚直に、親書は「前」大統領のものであることを伝えていたら、事態はどうなっていたであろうか。ここもまた、歴史の“if”への誘惑を禁じ得ない一コマである。
おわりに
著者は、本書の冒頭で、「日米関係の創成期の歴史を今日改めて振り返るにあたり、……彼(フィルモア)が偶然かつ短命の大統領であったにもかかわらず、与えられた内外の機会を捉え、米国内で彼の登場以前からあった各方面への日本への関心を政府としての本格的な政策として取りまとめ推進したことを客観的に理解することが重要である」と述べているが、その目的は十二分に果たされたと言えるだろう。「運命の女神(forutuna)
は後頭部が禿げている」と言ったのはマキャベリだが(『君主論』)、内外の機会を捉えて政策に落とし込んでいったフィルモアは、まさに的確に運命の女神の前髪を掴んだ指導者と言えるだろう
フィルモアのもとで初めて日本は太平洋の対岸の国として認識され、時を経て、第二次世界大戦後は、通商のみならず安全保障の観点からも、米国にとってかけがえのない存在と認識されるようになった。その重要性は、「日本は、アラスカ国境から広大な太平洋のへりを通り、アジアの南まで伸びる米国の死活的利益が存在する『巨大な三日月』の中心部になるように運命づけられていた」(マイケル・シャラー)と形容されるほどになり、今では「日本との同盟はアジアの平和と安定の要石(cornerstone)」とも称されている。
だが、米国は、刻一刻と姿を変えている。米国の人口の重心は今も西進し続けており人口動態の観点からも太平洋岸の重要性は右肩上がりである。だが、その太平洋岸では、アジア系米人、特に中国系と韓国系米人の割合が急増する一方で、日系米人の割合は減少し続けており、このことが、日米間の人的ネットワークの希薄化に繋がっている。「日米同盟の静かなる危機」(ケント・カルダー)である。 そうした米国内の変容を背景に、この先、米国の人々が太平洋越しに日本に向ける眼差しは、どのように変化していくのであろうか?日本は、今後も、米国にとって「アジアの平和と安定の要石」であり続けるのか、それともG2の狭間で苦悩する往年の経済大国にすぎなくなるのか、あるいは足早に通り過ぎる運命の女神の前髪をすかさず掴んで存在感を発揮する能動的な同盟国になっているのか。「来し方」を検証しながら、その実、様々な「行く末」のシナリオを想像させずにはおかない書籍である。
