松浦晃一郎著『アジアから初のユネスコ事務局長』 (日本経済新聞出版、2021年)
関場誓子(霞関会副理事長・聖心女子大学名誉教授)
はじめにー日本の存在感低下への警告の書
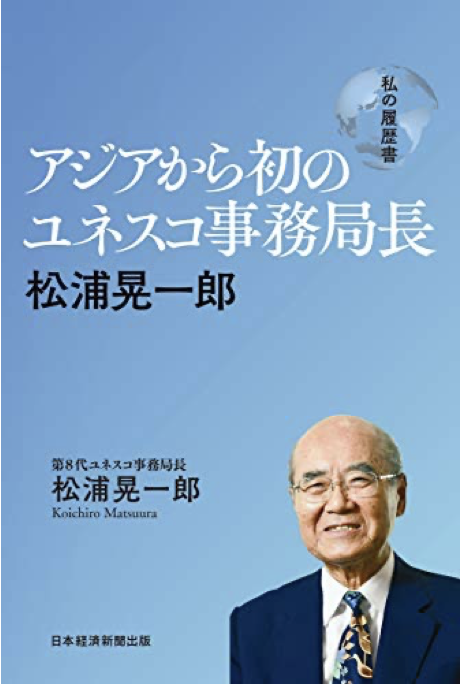
本書は、40年にわたる外交官生活の後、2期10年にわたってユネスコ事務局長を務めた松浦晃一郎氏(以下著者)による人生の旅路の書であり、それと同時に国際社会で存在感を低下させつつある日本の現状に対する痛烈な警告の書でもある。
本書では、幼少時代を皮切りに、東京大学での学びを経て外務省に入省し、経済協力局長、北米局長、外務審議官、さらには駐仏大使等の要職を務めた後、アジア初のユネスコ事務局長としてユネスコの改革に尽くした著者の人生の旅路が、穏やかな筆致で描かれている。読者は、あたかもロードムーヴィーを見るように、著者と旅路の風景を共にする。
だが、本書は単なる回顧録ではない。その穏やかな筆致とは裏腹に、著者が指摘する日本の立場、すなわち国際社会における存在感の低下という現実は深刻である。本書の冒頭で著者は、IAEAの天野之弥事務局長の逝去によって「主な国際機関でトップを務める日本人はひとりもいなくなった」(本書が出版された2021年春現在)という現実に触れ、国際機関のトップ争いが激化する中、「そのような争いに参加できる真の国際人を育成する体制を、国を挙げて早急に整える必要がある」と訴える。
求められる「国を挙げて」の対応
それでは、著者の言う「国を挙げて」とはどういうことか。
本書には、1998年に、日本政府からユネスコ事務局長への立候補を打診された著者が、3回にわたる選挙を勝ち抜いて、翌年11月に就任するまでの日本政府の奮闘ぶりが詳述されている。著者に白羽の矢を立てたのは、当時の外務大臣小渕恵三だった。小渕外相は著者の学習院中等科の同級生で、著者に、駐米大使、UNDP総裁、そしてユネスコ事務局長の選択肢を提示したという。著者が選んだのは、もっとも険しい道のりのユネスコ事務局長への立候補だった。挑戦への火ぶたが切られた瞬間である。
「君は学校の成績は俺よりもよかったが、選挙は俺が上だ。衆議院に12回連続当選の俺が選挙の総司令官をしてやる」
小渕外相による、この檄で始まる選挙戦の過程は手に汗握るものがある。同98年7月に小渕氏が首相になったことで参謀役は鈴木宗男官房副長官に委ねられたが、その後も小渕氏は一貫して総司令官として指揮をとり続けた。さらに高村外相はもとより、日本ユネスコ友好議員連盟の森喜朗会長、麻生太郎副会長を始め、政、財、学各界を挙げての応援態勢だったという。まさに「国を挙げて」の戦いだった。「国際機関の選挙では、候補者のよしあしだけでなく、国を挙げて応援するかどうかがとても大切だ」という著者の指摘が一般論に留まらない重みを持つのも、本書を通して「国を挙げて」取り組んだ日本政府の意気込みと息遣いがひしひし伝わってくるからである。
小渕首相の陣頭指揮の下、1999年にユネスコ事務局長に就任した著者は、翌年3末から一時帰国して首相に再会した。首相が倒れたのは、その深夜のことであり、翌月不帰の人となった。
「4月1日の教育相会合の席で話したのが、半世紀つきあった友との最後の会話になった」。本書で、もっとも切ない部分である。
その後日本は、2009年に天野之弥氏をIAEAの事務局長に、また2012年に関水康司氏を国際海事機関(IMO)の事務局長に送り込んでいるが、それ以降は10年の長きに渡って専門機関のトップ争いに敗北または不戦敗を続けていた。それは即ち日本には、かつて著者をユネスコに送り込んだ時のような「国を挙げての戦い」という気概や戦略が欠如していたことを意味するのではなかろうか。
「国を挙げての戦い」に敗れた例として著者が挙げているのが、2006年の世界保健機関(WHO)の事務局長選挙である。この時日本は尾身茂氏を擁したものの、中国が推す陳馮富珍に敗れている。「(尾身氏は)WHO西太平洋地域事務局長などを務め、実績は十分だったが、中国の国を挙げての選挙運動の前に敗れた」のだという。著者は、WHOのトップの座に狙いを定めた中国が、時間をかけて、周到な準備のもとに目的を達成した模様を、次のように語っている。
「中国政府はその4年前に彼女を香港衛生署長からWHOの伝染病担当の事務局長補に送り込んでいる。当時WHOトップは韓国が占めていたが、事務局長選挙をにらんで英語ができる人材に経験を積ませていたわけだ」
中国は、その後15の専門機関の内4機関でトップを占めるようになったが(2021年8月以降は3機関)、その事実こそ、まさに「国を挙げて」の周到かつ戦略的な取り組みの成果に他ならない。本書には日本の針路を考える上での手がかりが随所に見受けられるが、この部分も、「国を挙げて」とはどういうことかを考える上で極めて示唆的である。
「ユネスコ事務局長を退任し、日本に戻ってきてから、国連の諸機関の人事の状況を政府として把握しておくことが必要であると繰り返し助言した。どの機関のトップの座がいつ空白になるのかを早めに把握し、そのポストにふさわしい人材を時間をかけて育成しておくことが必要である。このまま『国連システム』での日本人トップの不在が続けば、国際社会における日本の存在感は低下していく」。著者の指摘は切実である。
本書が出版されて間もない2021年8月、万国郵便連合(UPU)の国際事務局長選挙が行われ、日本郵便常務執行役員の目時政彦氏が選出された。日本人による国連専門機関のトップ就任は、先述の関水康司氏以来10年ぶりである。「どの機関のトップの座がいつ空白になるのかを早めに把握し、そのポストにふさわしい人材を時間をかけて育成しておくことが必要」という、著者の訴えが奏功した結果と言えよう。
国際社会における存在感とは何か
それでは、国際社会における日本の存在感とは何か。著者は、「国際機関の長は世界全体を見回す立場であり、日本のために行動するわけにはいかない」と述べつつも、「とはいえ、世界の舞台に立っている日本人がいるといないとでは大きく違う」と指摘する。存在感の増大は影響力の強化に通じる。それだけではない。トップの振る舞い次第では、その機関の政策がトップの出身国の意向を反映した方向に舵を切る可能性は排除できない。本書で触れられている「キャビネ」の存在も気にかかる。
キャビネとは国際機関の事務局で中核を占める補佐官室のことで、「トップに就くと、出身国から補佐官室スタッフをたくさん連れて行く人が少なくない」という。本書には、「潘基文国連事務総長の場合、キャビネの韓国人側近と韓国語で相談することが多く、他のキャビネのメンバーは口を挟みにくかった」という例も挙げられている。多くの重要案件が、一握りの側近との協議で方向付けられていく事例は、古今を問わない。存在感という概念が政策という形になる過程で、このキャビネの役割にも看過し得ないものがある。因みに、著者は、就任時に日本語文書を扱う女性秘書ひとりを公募で雇った以外、キャビネ(35人)に誰も連れて行かなかったという。10年に渡る在任中、著者のもとで多くの改革が実施された。幾多の抵抗に会いながらも、諸改革が実現したのは、そうした公平な姿勢が評価されたためであろう。
ユネスコでの2期10年
2期10年にわたる在任中、著者は、組織や運営方法の抜本的な改革を実行するとともに、米国のユネスコ復帰、文化の多様性重視、基礎教育の普及、自然科学分野における水資源問題への注力等、多くの課題に取り組んだ。本書には、著者がそれらにどのように対処したかが具体的に記されており、ユネスコの役割、さらには国際機関での仕事とはどういうものかを理解する上での道標にもなる。国際機関勤務を志す若い世代にとっても必読の書と言えるだろう。
在任中に著者が手掛けた改革や政策は、その多くで40年におよぶ外交官生活の経験や人脈が十二分に活かされている。著者が最重要課題の一つと位置付けた米国のユネスコ復帰はその典型だが、対米関係以外にも、外交官時代のアセットが活かされた事例は枚挙にいとまがない。なかでも注目されるのがアフリカとの関係である。
「ユネスコ活動の対象としてアフリカに最重点を置こう」
事務局長に就任した際の著者の決意である。外交官人生の最初の任地が西アフリカだったことがアフリカへの深い理解と思い入れに繋がっており、アフリカ重視の姿勢は、任期1期目でほとんどのアフリカ諸国を回って基礎教育の普及やアフリカ独自の文明の世界遺産登録に尽力したことにも現れている。2期目を目指した際、アフリカ連合(AU)が「アフリカのために一生懸命働いてくれた」ということで連合の統一候補として著者を推薦したのは、そうした蓄積の賜物である。
日本の外務省がホームページで強調しているように、アフリカには、世界の国の約3割にあたる53ヶ国が存在し、「国連総会や国際機関の要職の選挙など、過半数や3分の2の多数決で意思決定が行われることの多い国際場裡においては、アフリカの動向は非常に重要」となる。特に、「2002年のアフリカ連合(AU)設立以降は、『アフリカの統一と団結』の下、53ヶ国がまとまった投票行動をとることが多くなり」、数の重みは増している。著者が再選を目指した際のAUの行動は、まさにそれである。
著者にとってアフリカは、外交官人生出発の地であると同時に、戦略的にも重要な地だったのである。
在任中、著者はメンバー国の首脳と頻繁に交流しているが、これら首脳についての人物評も興味深い。例えば、リビアのカダフィ大佐についてである。在任中延べ5回にわたってリビアを訪問した著者は、カダフィが「国の統一を維持しつつ経済発展を進めるために部族対立を強権的に抑え込んでいた」開発独裁の指導者であったとしつつも、「独裁が国の統一維持と経済発展に大きく寄与したことは間違いない」として、カダフィ施政の肯定的側面にも目配りしている。カダフィと言えば、「ならず者国家」(1994年クリントン大統領ほか)の指導者であり、ついにはその強権的統治ゆえに「アラブの春」で命を落とした独裁者。これが国際社会の、特に西側諸国のカダフィ像である。だが、「アラブ諸国で最初に国家の近代化に成功した指導者」という、著者のカダフィ評には、そうした一面的な見方とは一線を画した眼差しが見てとれる。
そのほか、プーチン大統領との度重なる交流など、本書には、一眼的視点では見落とされがちな、首脳たちのもう一つの表情が描かれている。
おわりに
近年、地政学の復活が叫ばれる。かつてハルフォード・マッキンダーは「東欧を制するものはハートランド(ユーラシア中央部)を制し、ハートランドを制するものは世界島を制し、世界島を制するものは世界を制する」と主張し、これに対しニコラス・スパイクマンは「リムランド(ユーラシア沿岸部)を制するものはユーラシアを制し、ユーラシアを制するものは世界の運命を制する」と主張した。習近平の進める一帯一路は、ハートランドとリムランドの両方をカヴァーし、さらにはアフリカから南米大陸にも及んでいる。地政学上の影響力拡大は、当然のことながら国際機関トップの選挙で有利に働く。そして国際機関における存在感の拡大は、地政学上の立場を有利にする。相乗効果である。
もとより、日本政府も手を拱いているわけでは無論ない。2021年2月には内閣官房と外務省の共同議長の下、「国際機関幹部ポスト獲得等に戦略的に取り組む」ための第1回関係省庁連絡会議が開催された。「国際秩序やルール形成を主導するに当たり、国際機関において、邦人がトップを含む重要な幹部ポストを獲得できるよう、また、優秀な人材を積極的に輩出できるよう、長期的な視野に立ち、候補者擁立等に関する省庁横断的な総合調整及び官民の人材の派遣や人材育成に関する検討を行う(外務省HP)」というのが、この会議の目的である。
首相自ら「俺が選挙の総司令官をやる」と意気込んだユネスコ事務局長戦の熱気とは比ぶべくもないが、ユネスコのトップ争いの際は首相と候補者(著者)が長年の親友だったという稀有な側面があった以上、政府として戦略的に取り組む仕組みが出来つつあるということは前進と言えるだろう。
中国は、地政学的思惑と時間的深慮の中で、言い換えれば時空間的ダイナミズムの中で個々の案件を動かしている。一帯一路も国際機関のトップ争いも、そうしたダイナミズムの中に位置づけられている。
「国際機関のトップを狙うには、国として人材を育て、支えていくことが大事になる」という著者の訴えが活かされるか否かは、政府のいう「戦略的に取り組む」姿勢を如何に時空間的ダイナミズムの中に組み込んでいけるかにかかっている。「オール・ジャパン」の真贋が試されるのはこれからである。
